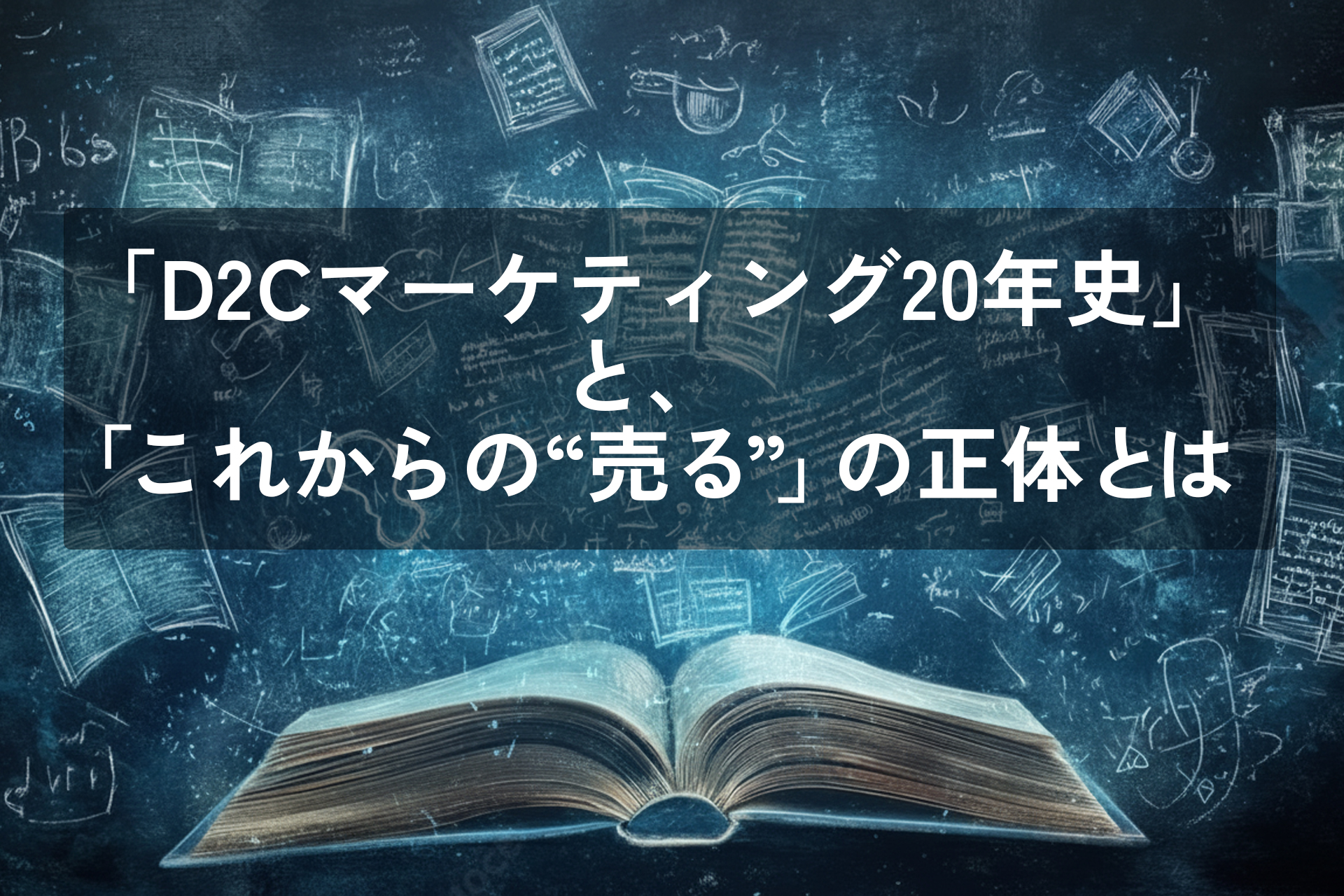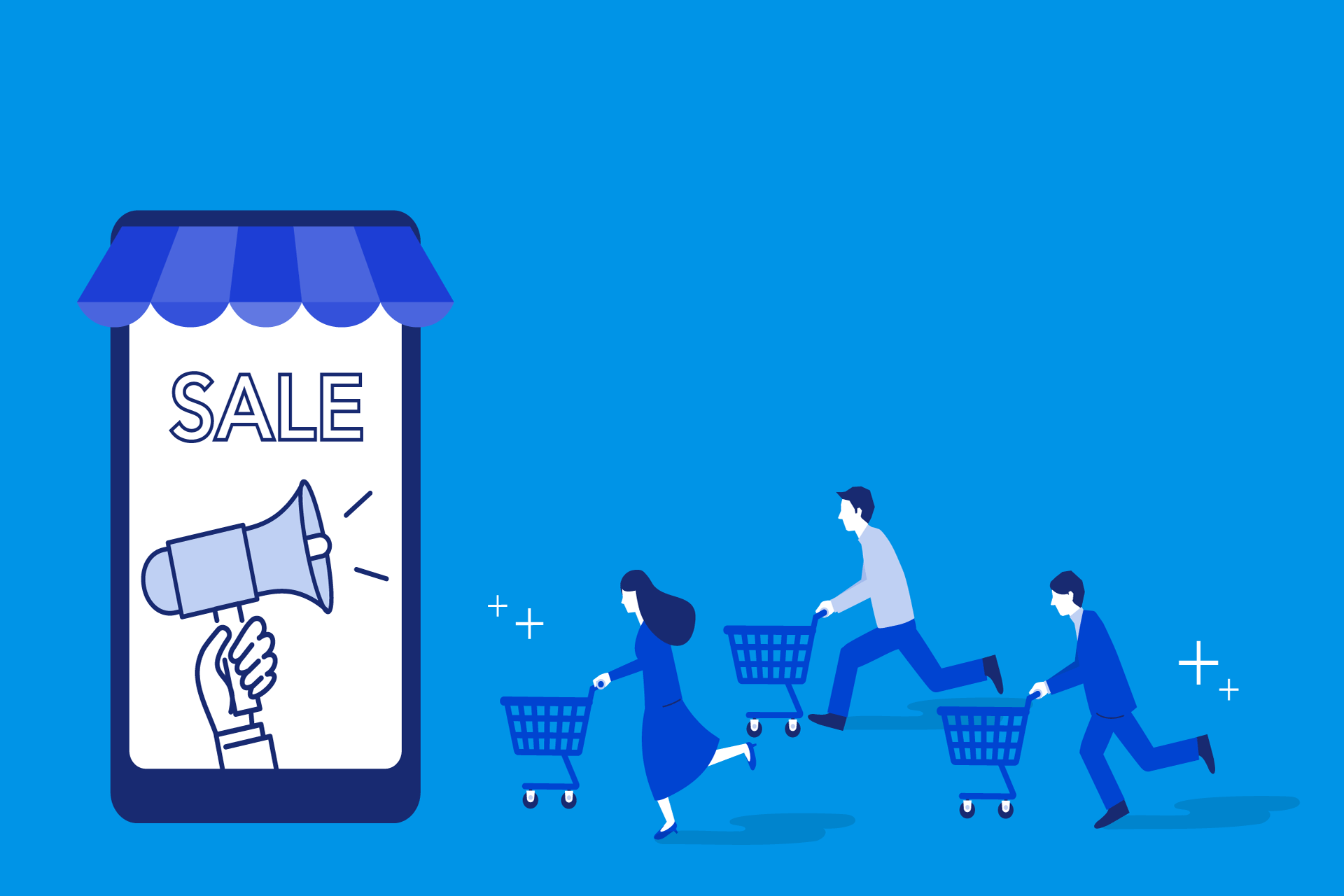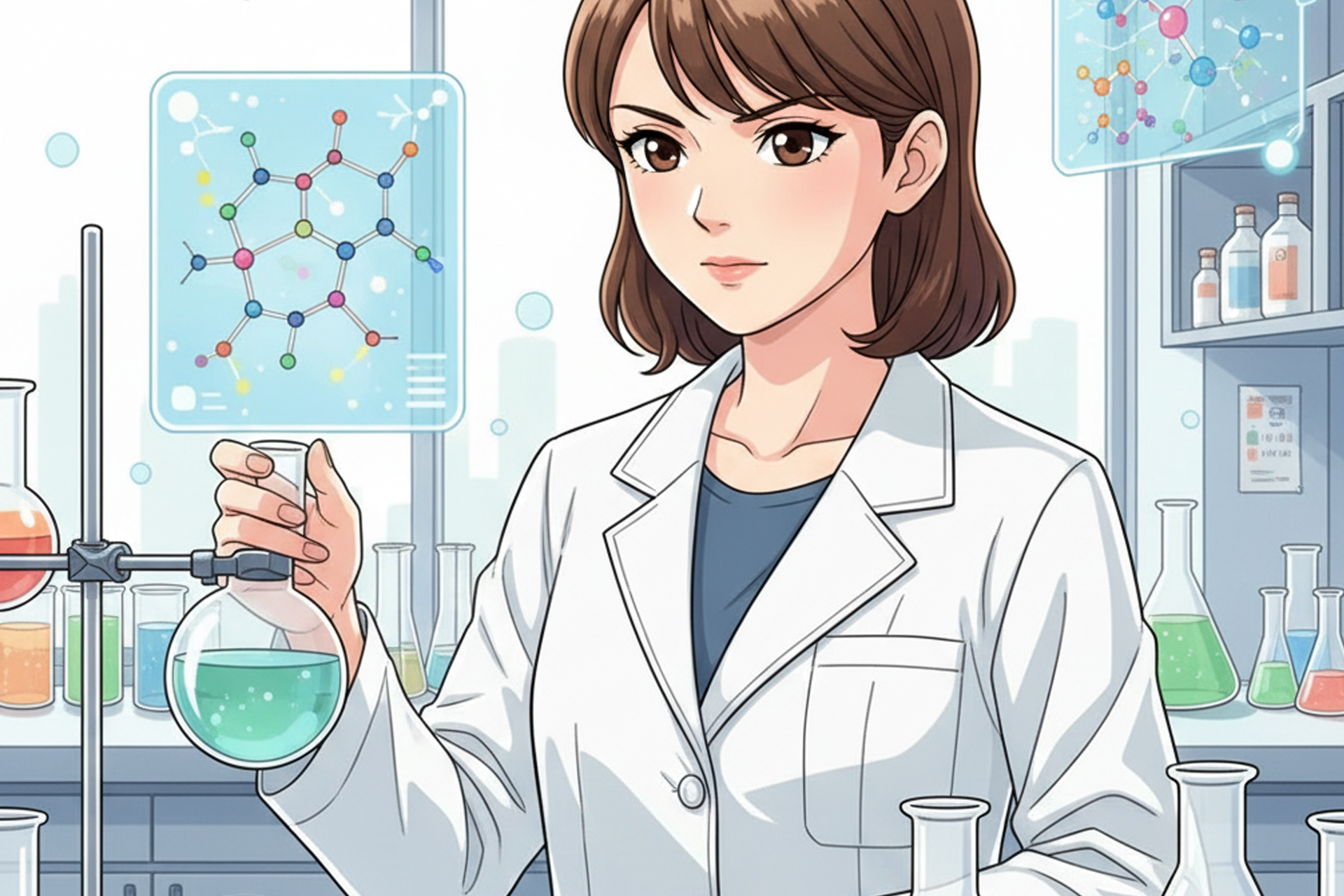「モノが売れる理由」が、根っこから変わってきた。
当時はまだ『通販』って言葉が主流の時代、私自身がむしゃらに走ってきたので、売れたときの高揚感も、売れなくなったときの焦りも、全部味わってきました。
そして、ここ10年ちょっとで「モノが売れる理由」が、根本からゴロッと変わってきたと感じています。
みなさんもお分かりのとおり、海外巨大ECモールの台頭、体の一部のように侵蝕してきたスマホやSNS、そしてAIの進化。
私たちの生活、思考・行動(買い方)は劇的に変わってきていると思います。
では、「いま(現在)、そしてこれから(未来)、どうすればモノが売れるの?」という話を、私自身の経験も踏まえながら、肌で感じたD2Cマーケティングの歴史を勝手に語らせていただきます!

【約20年前】「価格」と「物珍しさ」がすべてだった時代
ECの世界は黎明期で、まだまだ「EC」とは言い慣れず、『WEB(インターネット)通販』と言っていた時代(私だけ?)。
私は当時東京におりましたが、「通販王国 九州」と言われていた九州勢の通販企業を注視しておりました。
『単品リピート通販』が主流で、単品集中型の戦略を徹底的に行い、各社が独自のノウハウでしのぎを削り、顧客をとにかく大事にするCRMが特徴です。
また、テレビ、ラジオ、新聞メインで事業展開していたオフライン専業の通販企業も徐々にWEB領域に参入してきた時代でもあります。
この時代の勝ちパターンとしては、、、
「他にはない珍しい商品を、とにかくお得な価格で売る」です。
例えば、
「◯◯成分配合美容液!今なら初回半額!」
などのオファーを出せば、WEB広告のCPAも今では想像できないくらい安かったし競合も少なかった。
ある意味オファーありきで「勝つ商品」、「負ける商品」がはっきりレスポンスに跳ね返ってきた時代でした。
ですので、利益率の圧迫、リピート率低下などの改善のために、分析(当時はPDCA)、CRM、LTVの考え方が浸透はじめてきた頃と思います。
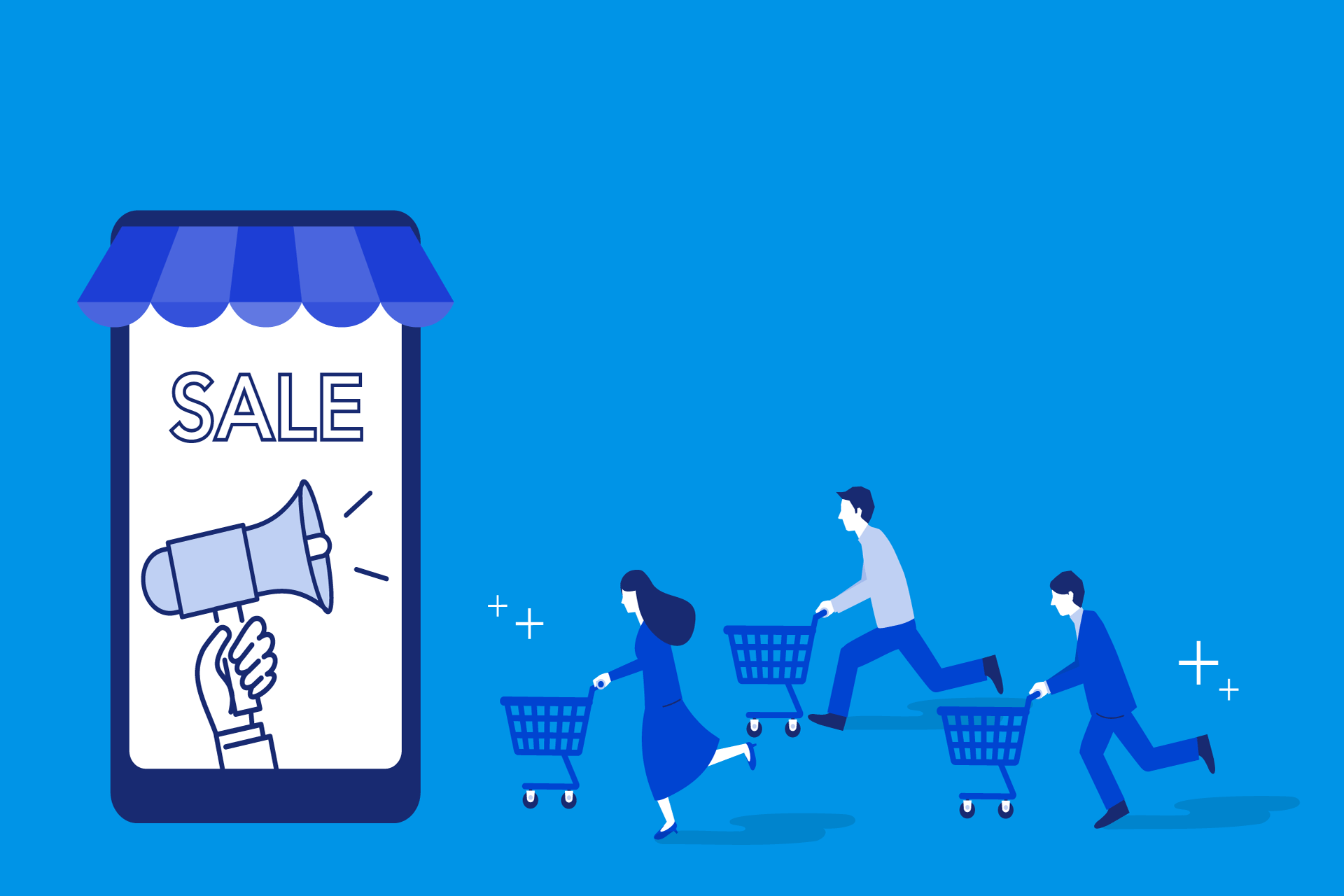
【約15年前】「機能性(ベネフィット)」で説得する時代
WEBでの通販(EC)市場には続々と多くのプレイヤーが参入し、東京の大資本を有する企業の参入(特に製薬会社など)で、市場は一気に群雄割拠の戦国時代へ。
そうなると「安い・珍しい」だけではユーザーが振り向いてくれなくなりました。
「この商品は“私”に、具体的に何をしてくれるの?」
という問いへの明確なANSER、つまり、「機能的なベネフィット」がレスポンスに影響しはじめたと実感しています。
「あの有名大学教授と共同開発した、この独自成分が、肌の奥にある〇〇に直接働きかけて、気になるシワがこうなるんです!」
(当時も薬機法は厳しかったのでこんなストレートには言えませんでしたが…)
このように、ロジカルかつ、科学的に、商品の優位性を説くマーケティングでした。
しかし、市場はプレイヤーで溢れ出していた事、ユーザーの目が肥えてきた事と、同時に経済が冷えきってしまった事で、財布の紐が固くなっていた時代でもあり、
「なるほど!この商品なら私の“あの悩み”を解決してくれそう!!」
といった、「納得感」や、それを裏付ける「販売ロジック」、「エビデンス」がマーケティングの主役だったかなと思います。
この手法は、進化しながら今でも続いています。
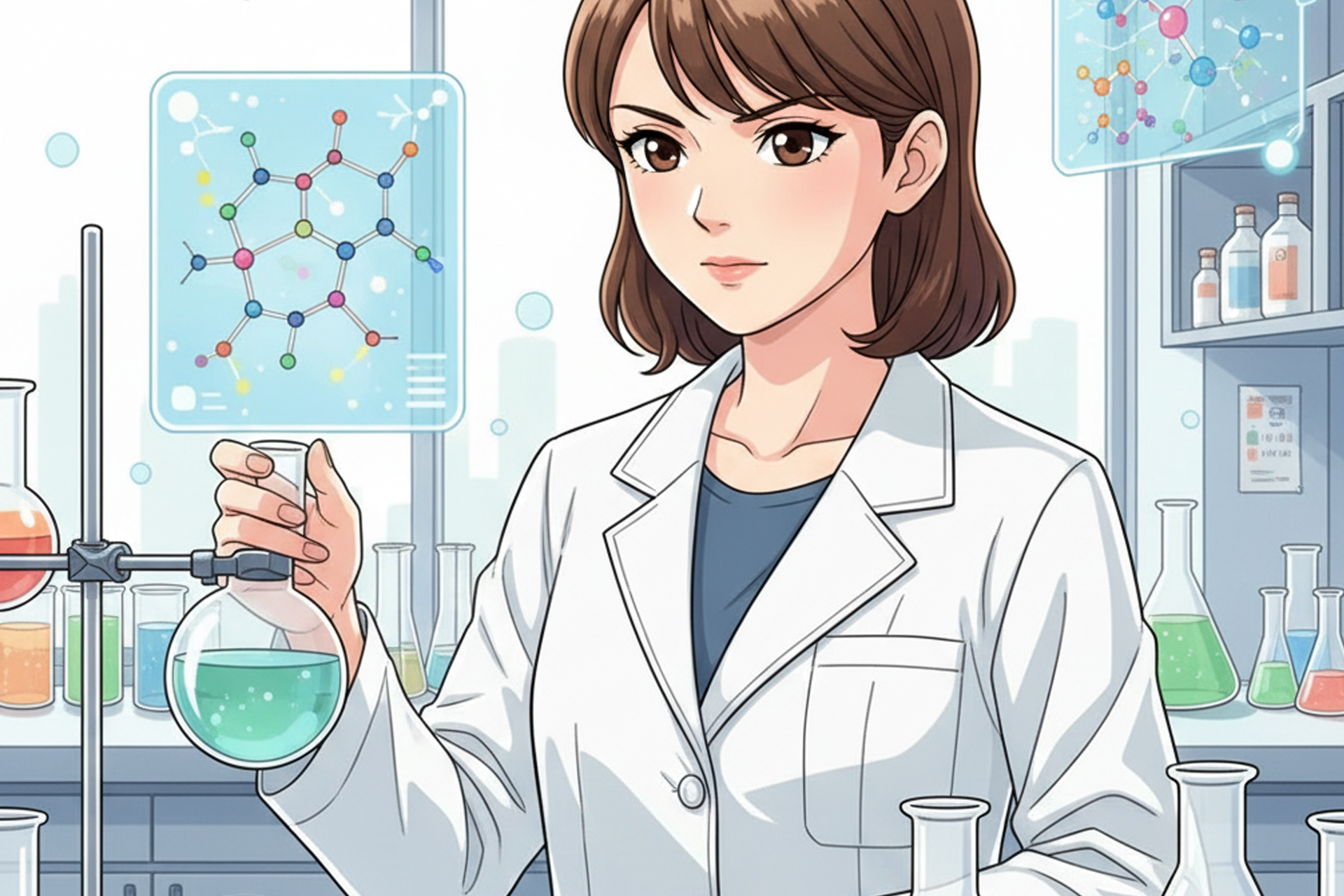
【約10年前】「ブランドと体験」に心酔した時代
この頃から、前段でお伝えした、機能性(ベネフィット)でさえも、コモディティ化(当たり前で差別化が難しくなった)してきた事もあり、非常に重要になったのが、ブランド(商品)の「世界観への共感」かと思います。
・このオーガニックコスメを使っている自分が好き
・このアウトドアブランドのメッセージに、いつもグッとくる!
・パッケージがオシャレで、持っているだけで気分がアガる!
などなど、SNS、特にInstagramの普及で「映え」の様に商品や体験が購買への強力なトリガーとなり、商品の機能を超えた「情緒的な価値」、いわゆる「体験(experience)」がマーケティングとして確立しはじめてきました。
「機能性(ベネフィット)」はもちろんですが購入する『意味』を売ることに重きが置かれ、『モノ消費からコト消費へ』などの言葉もこの頃かと思います。

【いま、そしてこれから】現在〜未来はどうすればモノが売れるのか?
価格で戦う時代が終わり、機能での説得も溢れかえり、オシャレなブランドや体験さえも当たり前になった。
広告費をかけても「どうせPRでしょ」とスルーされ、良いモノを作っても無数の商品の中に埋もれてしまう…。この課題に悩まれている担当者は多いのではないでしょうか。
「価格・機能性・ブランドや体験が当たり前になったこの時代、これからどのようなマーケティングをすればよいのか?」
私もこの途方もない問いに、ずっと向き合い続けて、最近やっと一つのヒントが見えてきました。
あくまで國嶋的考察ですが、そのキーワードとして、、、
『ストックホルム症候群』
ちょっと物騒な言葉ですが、例えば、銀行強盗の犯人と人質が一緒にいるうちに、なぜか心理的な絆を形成してしまう、あの心理現象です。
もっと柔らかく言うと『吊り橋効果』『ゲレンデマジック(古っ!)』でしょうか?
(わからない方は調べてみてくださいw)

要は、
ユーザー自体を『お客様側』ではなく、『こちら側』に引き込み(巻き込み)自分事化してもらう
これこそ、これからのマーケティングには必要なことかと思います。
「このブランドの考え方が、めちゃくちゃ最高におもしろい!」
「この店の〇〇さんの、商品愛がヤバすぎて、もはやファン!」
今まではこのあたりで止まっていましたが、ユーザーはすでに「買い手」側でいることに飽きており、本当に求めているのは、
「このブランドと一緒に、何かを仕掛けたい!何かおもろいことをしたい!」
「このコミュニティの一員でいたい!何か役割を果たしたい!」
「私にできる事があれば言って欲しい!はいよろこんで!」
そんな魂の琴線に触れる「心理(参加感)」が顕在化されつつあるかと思います。
あくまで私見ですが、成功された事例としては、今年の参議院選挙で大きく躍進した「とある党」です。(あえて党名は伏せます。)
「そもそも、今の日本ってマジヤバくない?」という、「問題意識」や「危機感」を徹底的に共有し、「公約を私たちみんなで一緒に考えよう!」と仲間(党員)を募る。
この思考プロセスは、今まで売り手側の一方通行であった、「機能性(ベネフィット)や「体験(experience)」だけではなく、ユーザーを巻き込んで『自分事(当事者意識)』として捉えてもらった結果だと思います。
「とある党」が議席を増やしたように、まさにその「個々の自分事化」が今後のマーケティングに必要な事かと考えます。

つまり、これからは企業が発信する情報や広告、インフルエンサーの「案件」など一方通行ではなく、ユーザー含め「熱狂する自分事化」を見つけ出し、その熱量を伝播させていく「コミュニティ」をデザインしていく「仕組み」の構築。
そして何より、企業自体もそのコミュニティの一員として、ユーザーと一緒に「熱狂する自分事化」という世界線で思いっきり遊ぶ(楽しむ)ことが重要になるかなと思います。
企業が「これ、おもしろいでしょ!」と一方的に提示するのではなく、ユーザーを巻き込んで、「これ、一緒にやったら、もっとおもしろいことになりません?」と問いかけてみる。
その魂の琴線に触れる『熱量の渦をデザイン』し、中心にいるのが、これからの「売れる」マーケティングかなと思います。
最後に。
このブログを書きながら、ハッとしました。
私が「株式会社ORENCH」を立ち上げた際、根底にあったのはコレだ!と。
当時は漠然としていて言語化できませんでしたが、今回、頭の中の整理になりました!
〜自分事化の熱量が、周りに伝播し、巻き込んでいく〜
『それ、おもしろそう!』それが、すべての原動力。
結局、人の心を本気で突き動かすのは、理屈を超えた原始的な衝動だと思います。
もし、今のやり方に限界を感じているなら、
もし、心の底からワクワクするような事をしたいと願っているなら。
オレンチと一緒に、最高に『おもしろいこと』、仕掛けませんか?
株式会社ORENCH 代表取締役 國嶋 利幸